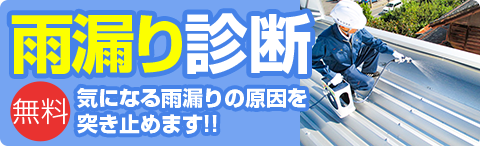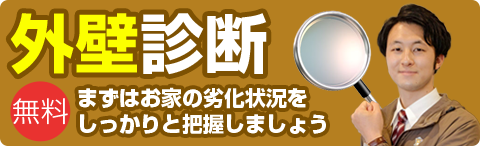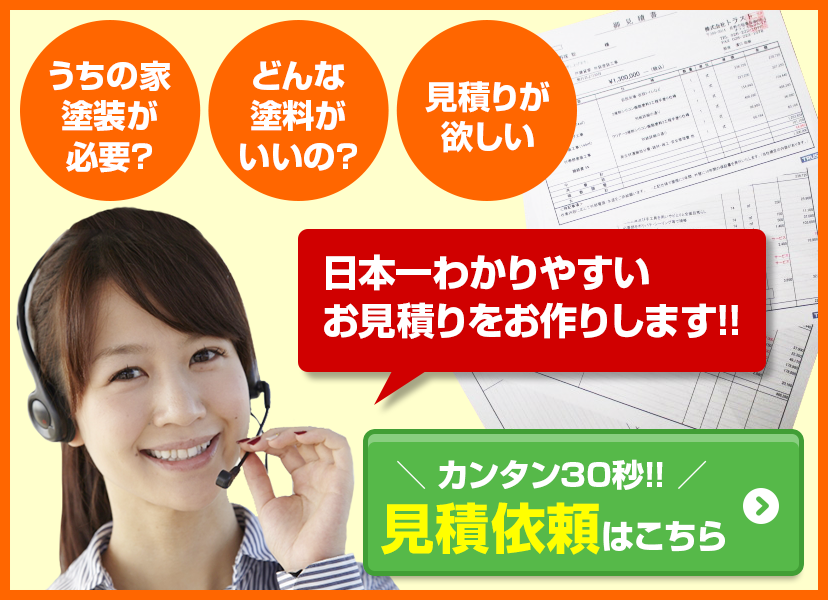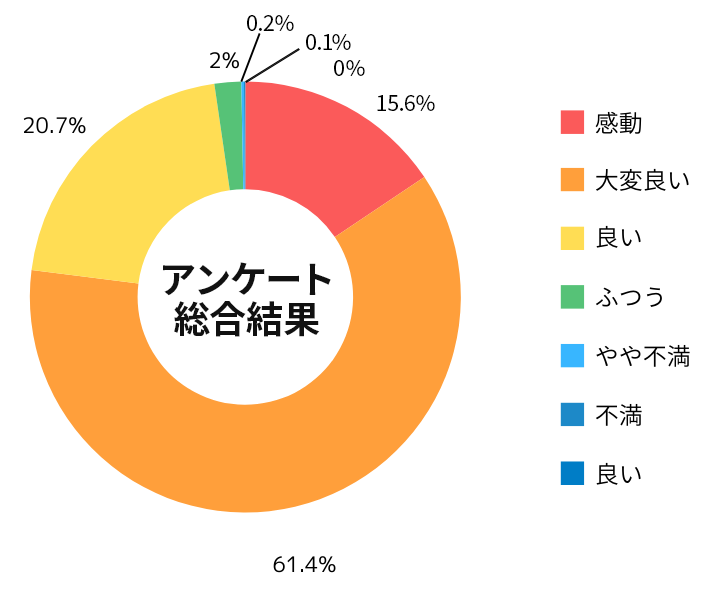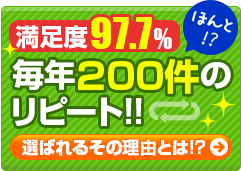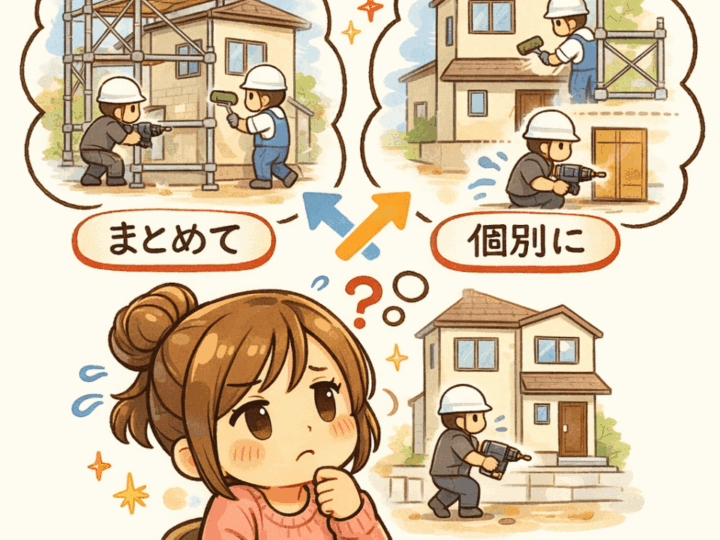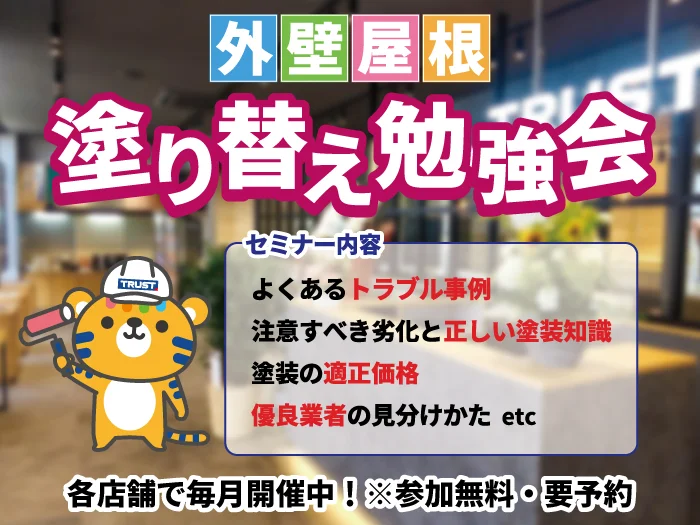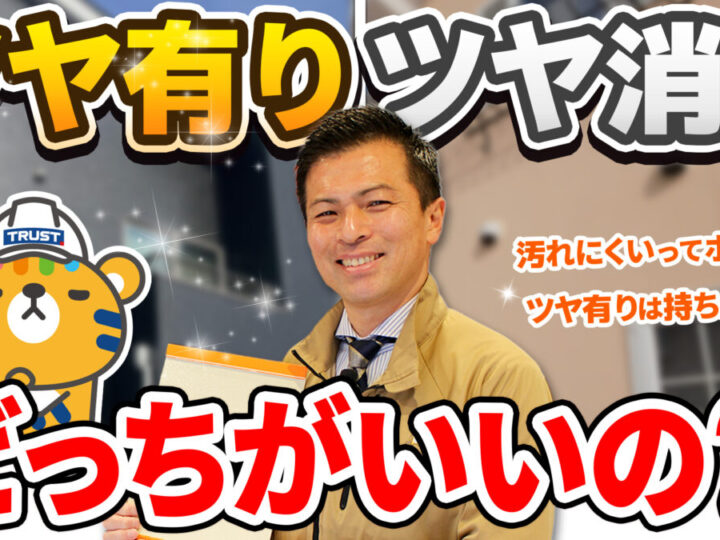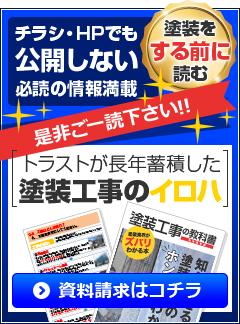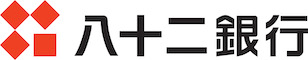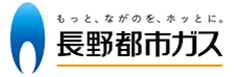2015.11.29 更新
海側の地域は塗装の劣化が早い?|長野市、上田市 外壁塗装・屋根塗装専門店トラスト
長野県長野市、上田市のみなさん、こんにちは! 地域密着の外壁塗装・屋根塗装専門店トラストです! お客様から、「外壁塗装の耐用年数は何年くらいですか」というお問い合わせをよくいただきます。 私どもでは、塗料ごとに目安となる年数をお答えしているのですが、これはあくまで目安であって、「住宅の外壁がさらされる環境によって異なってきます」ということも付け加えております。 「15年」持つと言われる塗料でも環境によっては15年も持たずに塗替えが必要になってくることも多いです。 特に、海側の地域は塗装の劣化が早い傾向があります。 自転車や自動車を所有されている方は実感しやすいのですが、外にカバーなど被せずに出しておくと、潮風を受けてサビなどが発生しやすくなってきます。 「塩害」と言い、海水に含まれる塩分が原因です。海水が蒸発した時に潮風に乗って塩分を含んだ空気が付着し、サビの発生や腐食の原因になっています。 特に鉄部には注意が必要で、サビの進行が早く、穴を空けてしまう事もあります。 屋根や外壁以外にも鉄製の雨樋なども注意してみた方が良いでしょう。 外壁や屋根の塗装を行う際には、こうした点も考慮する必要があるといえるでしょう。 海沿いの住宅だけでなく、「日射量の多い地域」「降雨量の多い地域」「豪雪地帯」などご自身のお住いの環境もしっかりと考えたうえで塗料を選ぶことも大切です。 塗装後のメンテナンスについては、年数だけで判断するのではなく、実際に壁や屋根の状態をこまめに点検して、適切な時期に塗装を行うことが大切になってきます。 トラストは外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店です。 長野県長野市、上田市地域密着で多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。 地域密着だからこそ実現できる適正価格で高品質な塗装をご提供いたします。これまで積み重ねてきた信頼と実績に恥じぬよう、誠心誠意対応させていただきます。 ★トラストは長野市、上田市で気軽に相談ができる《外壁・屋根塗装ショールーム》を展開しております★ 外壁塗装・屋根塗装・雨樋・雨漏り・サイディングなどでお困りの方はお気軽にどうぞ! 優良店・口コミ評判店目指して頑張ります(^^) 【外壁・屋根塗装専門店トラスト】についてはコチラ! 【お問い合わせフォーム】はコチラ!! 【よくある塗装に関するご質問】はこちらにまとめさせていただきました。 【よくあるご質問】はコチラ!!
続きはコチラ