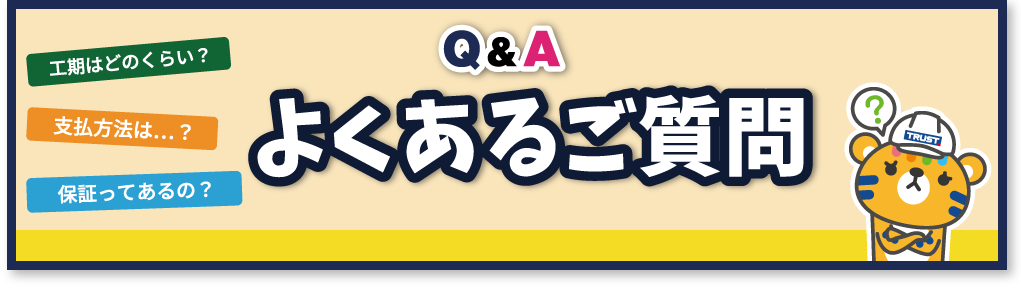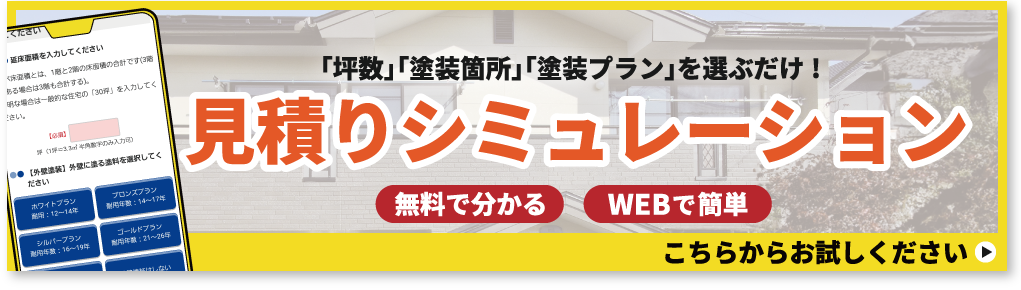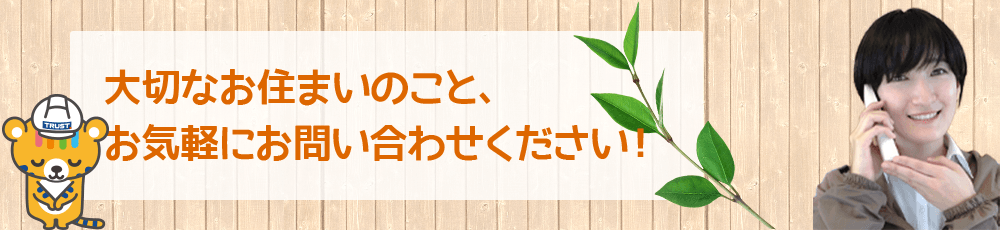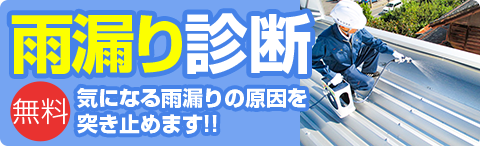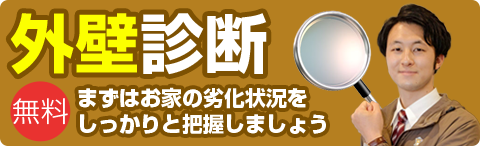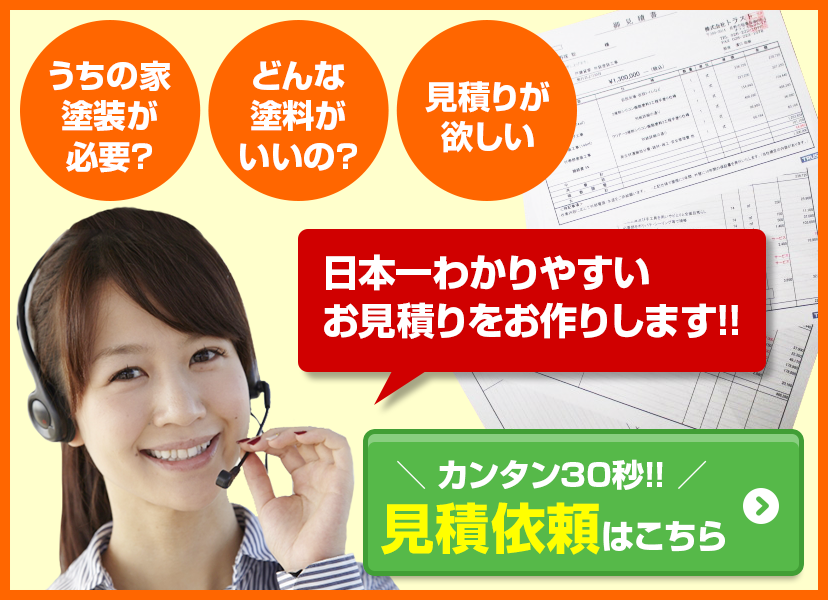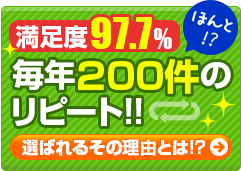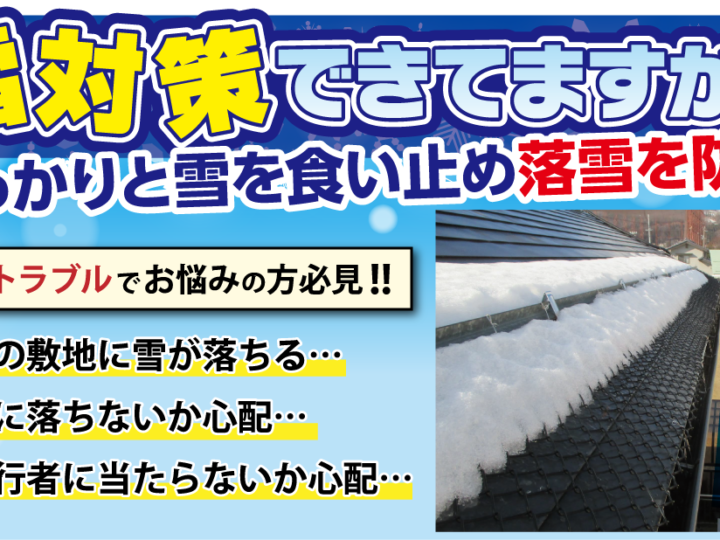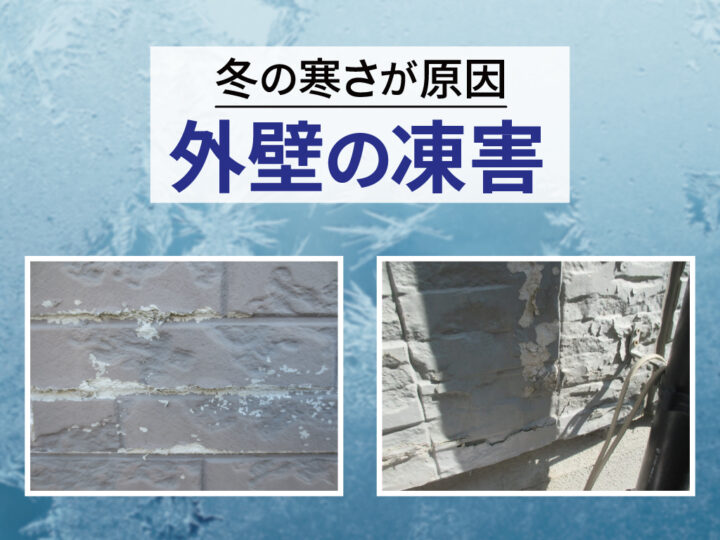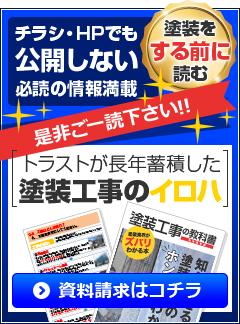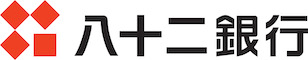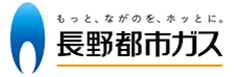木部塗装の工程とは?塗りつぶし仕上げのポイントをご紹介
2020.07.13 (Mon) 更新
今回は、現場で木部塗装を行った様子をご紹介します。
木材を塗装する際には「木目を活かす仕上げ」と「塗りつぶす仕上げ」の2通りがあり、今回の現場では塗りつぶし仕上げを採用しました。
塗りつぶしの場合には下塗り材の選定や塗り方に技術が求められ、仕上がりに大きな差が出てきます。
長野県長野市、上田市、佐久市のみなさん、こんにちは!
目次
木部塗装の2つの仕上げ方
木を塗る場合、大きく分けて以下の2つの方法があります。
木目を活かす塗装(浸透型)
木の風合いを残しながら塗料を染み込ませる方法で、自然な質感を大切にしたい場合に使います。下塗りは基本的に行いません。塗りつぶし塗装(造膜型)
木目を見せずに色を均一に塗る仕上げ方で、今回はこちらを採用しました。屋外や店舗の什器など、見た目の統一感を出したい場合に適しています。
塗りつぶし仕上げの工程と注意点
今回の作業工程は以下のように進みました。
1. ケレン(研磨)作業
まずは表面の汚れや古い塗膜を落とすために、木部をしっかりと研磨します。
ケレンを丁寧に行うことで、塗料の密着性が高まり、仕上がりも長持ちします。
2. 下塗り材の塗布

塗りつぶし仕上げの場合、必ず木部用の下塗り材を使用します。
木材は塗料をよく吸い込むため、下塗りをしておかないと、仕上げ時に吸い込みの差が出てムラが目立ってしまいます。
3. 仕上げ塗装

下塗りがしっかり乾いたら、仕上げ色を塗っていきます。
木材は吸収が早い素材なので、一気に繋げて塗らないと継ぎ目が目立ちやすくなります。スピードと丁寧さのバランスが求められる場面です。
4. タッチアップ(確認と補修)

仕上がった後は、塗り残しやムラがないかを細かくチェック。
必要に応じて補修(タッチアップ)を行い、見た目を整えます。
刷毛での仕上げに込められた職人の技
木部塗装では、基本的に刷毛のみで仕上げることが多いです。
ローラーやスプレーでは出せない繊細な表現が可能だからです。
特に塗りつぶしの場合は、仕上がりの美しさ=職人の腕の見せどころ。
一見簡単そうに見える作業でも、実際にやってみると意外と難しく、緊張感を持って行う必要があります。細かい部分まで気を配りながら、丁寧に仕上げていくのがプロの仕事です。
トラストは外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店です。
長野県北信・東信地域密着で多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
地域密着だからこそ実現できる適正価格で高品質な塗装をご提供いたします。
これまで積み重ねてきた信頼と実績に恥じぬよう、誠心誠意対応させていただきます。
★トラストは長野市、上田市、佐久市で気軽に相談ができる《外壁・屋根塗装ショールーム》を展開しております★
外壁塗装・屋根塗装・雨樋・雨漏り・サイディングなどでお困りの方はお気軽にどうぞ!
優良店・口コミ評判店目指して頑張ります(^^)
ブログ執筆者

株式会社トラスト 施工部
酒井 裕大
所有資格:
- 一級塗装技能士
- 職長・安全衛生責任者